2018年度施政方針(2018年第1回燕市議会定例会)
2018年2月28日に開会した第1回燕市議会定例会において、鈴木力市長が2018年度施政方針を発表しました。
ここでは、その全文を掲載します。
- 【はじめに】
- 【戦略1 定住人口増戦略】
- 【戦略2 活動人口増戦略】
- 【戦略3 交流・応援(燕)人口増戦略】
- 【戦略4 人口増戦略を支える都市環境の整備】
- 【持続可能な行財政運営】
- 【むすび】
【施政方針演説(全ページ)】 (PDFファイル: 454.3KB)
【新年度予算の概要(施策別)】 (PDFファイル: 3.4MB)
2018年2月28日
第1回燕市議会定例会
2018年度施政方針
燕市長 鈴木 力
はじめに
2018年第1回燕市議会定例会にあたり、新年度に臨む私の市政運営の基本方針並びに主要事業について申し述べます。
私が燕市長に就任して間もなく2期8年が経過しようとしています。この間、私が一貫して目指してきた都市像は、「日本一輝いているまち・燕市」でした。
それは、産業、教育、スポーツ、福祉、環境など様々な分野で市民活動や企業活動が活発に行われ、全国の人から「やるね!燕」、「凄いね!燕」と注目を浴びることにより、燕市に住む子どもたちが、ふるさとへの誇りと愛着、未来への夢や希望を持てるまちの実現であります。
振り返ってみますと、1期目においては、「燕はひとつ」を合言葉に、真の合併効果を目指して新生燕市の一体感の醸成に努めるとともに、産業の振興、教育・子育て環境の整備、医療福祉の充実などの課題に対し、新たなアイデアや工夫を加えながら積極的に取り組んでまいりました。
2期目においては、「燕よひかれ」というスローガンの下、「3つの人口増戦略」を柱とした第2次総合計画を策定し、人口減少に歯止めをかけ、地域の活力を維持・発展させていく施策をスタートさせ、現在も進行中であります。
この総合計画に登載した各施策については、成果の濃淡はあるものの、概ね順調に進捗しており、引き続き着実に実行していかなければなりません。
2018年度は、第2次総合計画の3年目にあたり、目標達成に向けて実績を積み上げる重要な年度に位置付けられます。
そのため予算編成にあたっては、雇用・就労を支える産業の振興、地域に根ざした教育の推進と子育て支援、健やかな暮らしを支える医療福祉の充実など、総合計画の戦略体系に基づく主要事業に対して、優先的に予算配分をさせていただきました。
さらに、総合計画策定後に顕在化してきた「子どもの貧困」、「小規模企業の事業承継」及び「人手不足」といった課題についても取り組みを開始することとしました。
特に、子どもの貧困問題につきましては、昨年、「ひとり親家庭等の生活実態に関するアンケート調査」を実施し、子どもにかかる費用への負担感や進学に対する希望と現実のギャップについて確認するとともに、既存の支援サービスの周知も含めて、相談体制充実の必要性などの課題を整理したところであります。
今後の具体的な施策については、既に就学援助として新入学児童生徒の学用品費の入学前支給を行うこととしましたが、クロス集計も含めた調査結果がまとまったばかりであり、また、国・県においても給付型奨学金の拡充をはじめ様々な施策の検討が始まっており、これらの動向も見極めたうえで、さらに掘り下げていく必要があります。
このため、新年度においては、当面の対策として既存の相談支援窓口の充実や地域食堂の開設も含めた子どもの居場所づくりへの支援活動を行う団体等の育成に向けた取り組みを実施するとともに、有識者や福祉・教育・子育て等の支援機関の関係者などで構成する「子どもの貧困対策検討会議」を設置し、基礎自治体として実施すべきさらなる施策を検討していきたいと考えています。
一方で、財政状況は厳しさを増しております。2016年度決算では、地方消費税交付金などの国からの依存一般財源が大きく減少したことなどにより、実質単年度収支が7年ぶりに大きくマイナスに転じ、財政調整基金残高も約3分の2まで一挙に目減りしました。今後も地域経済の現状から税収の大幅な伸びを期待することはできず、普通交付税においても、合併の特例期間が終了し、一本算定への完全移行に向け、段階的な縮減が始まっています。
したがって、2018年度当初予算は、本市の中長期的な財政状況を見据え、将来にわたり持続可能な財政基盤を維持していくため、歳入の縮減基調に合わせて、さらなる選択と集中を進める緊縮型予算を基本として編成したところでもあります。
当初予算の概要
それでは、2018年度当初予算案の概要についてご説明申し上げます。
初めに予算の規模についてです。一般会計予算案の総額は、397億8,000万円であります。2017年度と比較して4.1%、15億6,900万円の増額となり、歳入と歳出で同額計上している借換債の額を除いた実質的な予算規模におきましても、339億5,206万円となり、対前年度比で7.0%、22億902万円の増額となっております。
ただし、実質的な予算規模と国の2017年度補正予算(繰越事業)を合わせた執行ベースでの予算規模で見てみますと、340億8,944万円であり、対前年度比で3.2%、11億3,164万円の減額となっております。これは、直近10年間において3番目に小さい規模であり、緊縮型予算と申し上げる所以であります。
最終的に一般会計と5つの特別会計を合わせた当初予算総額は、595億9,356万円であり、対前年度比で0.6%、3億4,875万円の減額となっております。
次に、第2次総合計画の戦略体系に沿って、新年度の主要事業を説明いたします。
戦略1 定住人口増戦略
戦略の第1は、定住人口増戦略であります。
燕市に住みたい、働きたいと思う人を増やすために、
- 雇用・就労を支える産業の振興
- 地域に根ざした教育の推進と子育て支援
- 健やかな暮らしを支える医療福祉の充実
- 移住・定住の促進
という4つの基本方針に則り、各種施策を総合的に進めながら、燕市に住みたい、働きたいと思う人を増やしていく必要があります。
基本方針1 雇用・就労を支える産業の振興
定住人口増戦略の1つ目の柱は、「雇用・就労を支える産業の振興」です。
施策1 ものづくり産業の活性化
はじめに、「ものづくり産業の活性化」についてであります。
「燕市中小企業振興条例」を改正し、小規模事業者への支援強化を明確化したうえで、新たに産官金一体となった産業振興協議会を設置し、実態調査の実施や必要な対策の検討を行うとともに、金融・補助制度の新設や拡充、労働生産性の向上を目的とした設備投資に対する固定資産税の免除などにより、中小企業・小規模事業者の健全な事業運営や円滑な事業承継などを支援してまいります。
また、引き続き、国の地方創生推進交付金を最大限に活用しながら、新商品・新技術開発や販路開拓の支援、次世代経営人材の育成、次世代の産業形成に向けた取り組みを展開し、ものづくり産業を多方面から振興いたします。
2年後に迫る東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、オリジナルカトラリーを開発し、選手村での採用や一般向け販売を目指すなど、引き続き国内外に広く燕ブランドを発信するPR活動を展開してまいります。
インターンシップ受入れの先進地を目指す「つばめ産学協創スクエア事業」については、産業界が整備した宿泊・交流施設を活用し、その活動をさらに広げていきます。

(つばめ産学協創スクエア事業)
企業誘致につきましては、市内外企業への立地意向調査を行い、農振除外など長年の懸案となっている土地利用上の問題解決に向けて調査・研究を進めてまいります。
施策2 新たな産業育成・創業の支援
次に、「新たな産業育成・創業の支援」についてであります。
新たな創業支援策として、クラウドファンディング型ふるさと納税制度を活用した「ふるさと起業家支援プロジェクト」を創設し、地域活性化を推進する事業を立ち上げる起業家を支援してまいります。
また、引き続き「TSUBAME HACK!」などの共創型イベントを開催しながら、ローカルイノベーションを加速させる価値創造型の人材が生まれる土壌をつくり、将来的に燕市のものづくり産業と結び付けていくことを目指します。

(TSUBAME HACK!)
商業の活性化については、大学との連携により「小売商業みらい懇談会」を新たに立ち上げ、将来的な小売商業や商店街の在り方などについて検討を進めるとともに、商工会議所や商工会と連携し、小売商業・商店街の魅力向上に取り組む団体・個人を支援するほか、「ツバメルシェ」の開催により個店の魅力をPRしてまいります。
併せて、「燕青空即売会」や「燕三条トレードショウ」の開催等を通じ、卸売業や物流業の活性化にも取り組んでいきます。

(燕青空即売会)
施策3 変化に対応する農業の振興
次に、「変化に対応する農業の振興」であります。
2018年産から米の生産数量目標の配分が廃止されるなど、大きく変化する農業情勢に対応するため、新たに「水田経営力強化推進事業」として、業務用米や輸出用米など需要に応じた米づくりと水稲以外の高収益農産物の作付けを推進するとともに、省力栽培等による低コスト化への取り組みを支援し、農業所得の向上を図ります。

また、農業者の経営力向上を図るため、「先進技術活用推進事業」を新規に立ち上げ、ICTやドローン等を活用した先進技術の最新情報を提供いたします。
さらに、燕市のブランド米「飛燕舞」、「つば九郎米」などの主要な農産物や農産加工品の販路を拡大するため、ふるさと納税や東京ヤクルトスワローズとの連携に加え、燕市の農産物と首都圏の消費者とを繋ぐ取り組みとして「農産物販路拡大推進事業」を実施し、首都圏でのテストマーケティングなどを実施いたします。
「チャレンジ・ファーマー支援事業」では、経営規模の拡大により、新たに必要となった機械設備の導入等に対する補助制度を創設いたします。
引き続き、「若手農業者ステップアップ事業」により、主体的な農業経営に取り組む担い手の育成を図るとともに、「農商工連携ビジネス創出支援事業」により、農商工が融合した新たなビジネスチャンスの取り組みを促進いたします。



(2017年度に農商工連携ビジネス創出支援事業で開発された商品)
基本方針2 地域に根ざした教育の推進・子育て支援
定住人口増戦略の2つ目の柱は、「地域に根ざした教育の推進と子育て支援」です。
施策1 知・徳・体を育成する教育の推進
はじめに、「知・徳・体を育成する教育の推進」についてであります。
確かな学力の修得とグローバルな人材を育成するため、引き続き、「新潟大学教育学部とのパートナーシップ事業」や「中学生学力向上対策プロジェクト」、燕市独自の英語教育「Jack & Bettyプロジェクト」を推進するとともに、「地域に根ざす学校応援団事業」において、地域ボランティアと連携した放課後学習支援を強化し、子どもたちの学習の習慣づけや学力向上に努めてまいります。

(Jack&Bettyプロジェクト)
また、子どもたちが自ら意欲的に学べる環境を整えるため、ふるさと納税の寄附金を財源として、ICT機器を活用した教育の推進や、学校図書館の蔵書を充実させるとともに、読書に意欲的に取り組む児童に対する表彰制度を創設します。
さらに、「長善館学習塾」や「燕キャプテンミーティング」などの個性を伸ばす教育のほか、文部科学大臣表彰を受賞した「Good Jobつばめ推進事業」や「つばめキッズファーム事業」などのキャリア教育の充実を図り、体験を通じて、豊かな人間性や社会性など子どもたちの「生きる力」を育みます。

(長善館学習塾キャンプ)

(Good Jobつばめ推進事業)
併せて、小中学校の課外活動における指導の在り方や、活動時間の基準などを示したガイドラインを作成するとともに、中学校部活動において外部人材の活用を図ることにより、児童生徒と教員の双方にとって充実した部活動になるよう努めます。
県教育委員会に提出した「燕市内の県立高校の特色化に関する提案書」に基づき、地元高校が行う魅力ある高校づくりの活動を支援するとともに、「羽ばたけつばくろ応援事業」も引き続き実施し、地域人材の育成に努めてまいります。
食育の推進については、地元出身の料理研究家と連携した新しい給食メニューの開発や地産地消を進める「三ツ星給食プロジェクト」に取り組みます。
さらには、悩みを抱える子どもたちや若者が、問題解決に向けて前進できるよう、中学校卒業後も相談できる体制を継続するとともに、粟生津小学校大規模改造工事を行い、子どもたちが安心して学べる教育環境を整備します。
施策2 安心して産み育てられる子育て支援
次に、「安心して産み育てられる子育て支援」についてであります。
出産後の育児不安を軽減し、母子ともに健やかな生活が送れるよう、母親の休養や育児指導・サポートを受けられる宿泊型・デイサービス型の「産後ケア事業」については、委託医療機関を増やして利用促進を図るとともに、不妊治療費の一部助成を継続し、妊娠を望む夫婦を支援します。
園児数の減少や保育ニーズの多様化、園舎の老朽化に対応するため、分水小学校区の地蔵堂保育園と笈ケ島保育園を統合・民営化する新たな保育園の整備に着手し、平成33年(2021年)4月の開園を目指します。
また、仕事と子育ての両立を支援するため、「ファミリーサポートセンター運営事業」や「病児・病後児保育運営事業」に引き続き取り組むとともに、児童クラブの運営数の拡大を図るほか、保育士等人材バンクの設置により、保護者の一時保育のニーズに柔軟に対応できる体制の構築を目指します。
引き続き、要保護児童への支援や児童虐待の相談等に迅速・的確に対応するため、家庭児童相談チームと関係機関の連携体制の充実を図るとともに、研修会を開催するなどして相談員の資質向上に努めます。
基本方針3 健やかな暮らしを支える医療福祉の充実
定住人口増戦略の3つ目の柱は、「健やかな暮らしを支える医療福祉の充実」です。
施策1 医療サービスの機能強化
市町村の国民健康保険は、2018年度から都道府県が財政運営の責任主体を担うこととなりますが、資格管理、保険給付、保険税率の決定と賦課・徴収などの業務については引き続き市町村が担うため、今後も健全な財政運営に努める必要があることから、引き続き「医療費適正化事業」を重点的に推進します。
具体的には、これまでのジェネリック医薬品の普及促進や生活習慣病の重症化予防などに加え、新たに服薬管理の適正化を推進する「残薬・ポリファーマシー対策事業」に取り組みます。
県立吉田病院については、引き続き弥彦村と連携しながら、これまで以上に地域に密着した病院としての特色ある医療の提供と早期改築を県へ要望してまいります。
施策2 地域で支える高齢者福祉
次に「地域で支える高齢者福祉」についてであります。
2018年度からスタートする「燕市高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画」に基づき、団塊の世代が75歳以上となる平成37年(2025年)に向けて、高齢者が住み慣れた地域で安心・快適に生活できるよう、高齢者を地域で支え合う地域包括ケアシステムの構築を目指し、医療、介護、介護予防、生活支援等が包括的に提供される仕組みづくりに引き続き取り組んでまいります。
地域の支え合いを推進するため、生活支援コーディネーターを中心に「支え合い活動推進会議」を開催し、生活支援サービス提供体制の構築を図るほか、地域の元気な高齢者が活躍する場を提供し社会参加を促しながら、介護予防につなげていきます。
認知症対策については、認知症の方やその疑いのある方に早い段階で専門家による支援が受けられるよう、認知症初期集中支援チームを新たに設置します。
また、介護人材の確保のため、介護資格取得のための研修費用補助の対象に喀痰吸引等研修を追加するとともに、介護施設に継続して従事する若手職員の表彰制度を新設し、業務の魅力、やりがいの高揚と人材定着促進を図ります。
施策3 障がいのある人への切れ目のない支援
次に、「障がいのある人への切れ目のない支援」についてであります。
障がいのある人が地域で希望する生活を送り、ご家族も安心できるよう、相談支援体制の充実に取り組みます。
障がい者基幹相談支援センターでは、多様化・複雑化する相談ニーズに対応できる相談支援専門員を確保するとともに、相談支援事業所の機能強化を図ることにより、両者一体的な相談支援体制を構築します。
また、障がい者就労における働く場と工賃の確保に向けて、新たに施設外就労農業体験のモデル事業を実施することで「農福連携」を進めるとともに、就労移行後のサポートなどにより、福祉的施設から一般就労への移行・就労定着を図ります。
さらに、「障がい児通所支援事業」については、「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」に「保育所等訪問支援」を加え、サービスの充実を図ります。
療育支援の必要な人に対しては、切れ目のない支援を受けることができるよう保護者も含めた関係者が連携できる体制の構築を進めていきます。
基本方針4 移住・定住の促進
次に、定住人口増戦略の4つ目の柱である「移住・定住の促進」についてです。
施策1 移住・定住希望者へのサポート強化
燕市に移住する人を増やすため、首都圏などで開催される移住イベントで情報を発信するとともに、新たに県外からの移住者を対象とした家賃補助制度を創設するなど、移住先としての魅力強化を図ります。
引き続き、「東京つばめいと」の運営を行い、交流会やサポート活動、市内企業とのマッチングなどを通じて将来的なUターンに結びつけてまいります。

(東京つばめいと)
また、燕市への定住化を目的とした働き盛り世代や子育て世代などへの住宅取得支援については、このたび策定した「燕市立地適正化計画」に定める居住誘導区域への定住を重点的に促進する内容に一部条件を変更したうえで、引き続き実施します。
戦略2 活動人口増戦略
戦略の第2は、活動人口増戦略です。
- 市民が主役の健康づくり・生きがいづくり、
- 支え合い・助け合い活動の活発化、
- 若者・女性の力を活かしたまちづくり
を進めながら、地域社会の中でキラキラ輝く人を増やします。
基本方針1 市民が主役の健康づくり・生きがいづくり
活動人口増戦略の最初の柱は、「市民が主役の健康づくり・生きがいづくり」です。
施策1 元気を磨く健康づくり
はじめに「元気を磨く健康づくり」についてであります。
2018年度から始まる「第3次燕市健康増進計画」に基づき、自分のための健康づくりだけでなく、地域で積極的に健康づくりの啓発活動に取り組んでもらえる人材の育成を推進します。
また、5年目を迎えた健康づくりマイストーリー運動「つばめ元気かがやきポイント事業」では、メタボリックシンドローム対策を取組項目に追加するとともに、こども手帳の配付対象を小学校6年生までに拡大します。

(2017年度版)
さらに、疾病の早期発見・早期治療のための特定健康診査や各種検診、保健指導の充実に努めます。特に、「乳がん検診事業」については、検診車による集団検診に加え、新たに医療機関での個別検診を実施いたします。
併せて、「誰も自殺に追い込まれることのない、住みよく安心な社会づくり」を目指し、「燕市自殺対策計画」を策定いたします。
施策2 健全な心と体を支えるスポーツの推進
次に「健全な心と体を支えるスポーツの推進」であります。
「スポーツ拠点化推進事業」では、地域スポーツコミッション機能を充実させ、官民一体となって全国規模のスポーツ大会や合宿の誘致などを働きかけるとともに、地元食材を活用した「つばめアスリート弁当」を提供することにより、スポーツを通じた交流の促進と地域経済の活性化を図ってまいります。


「ホストタウン推進事業」では、2020年東京オリンピックに係る事前合宿の誘致に引き続き取り組むとともに、既にパラアーチェリーチームの合宿が決定しているモンゴル国とのスポーツ・文化交流を行います。また、小中学校においてパラアスリートによる体験型授業を開催し、障がいのある人との共生社会の実現やチャレンジする気持ち、諦めずにやりぬく心などを学びます。


施設整備につきましては、老朽化対策として、燕市民体育館の受変電設備やスポーツランド燕屋内運動場の外装、トイレの洋式化工事などを実施いたします。
施策3 心豊かな生涯学習・文化活動の充実
次に、「心豊かな生涯学習・文化活動の充実」についてであります。
引き続き、市の文化財等を紹介する映像プログラム「ブラつばめ」を制作公開し、市の魅力を市内外へ発信するとともに、学校のふるさと学習の教材として活用することで、郷土に対する誇りと愛着を育みます。


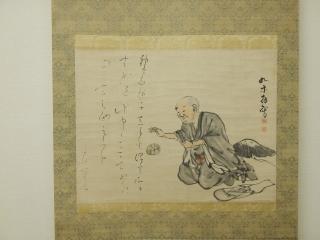
また、長善館史料館につきましては、筑波大学と連携して進めている歴代館主の日記解読作業の成果品を活用した特別展を開催するとともに、昨年設立した「長善館友の会」と連携した活性化策に取り組みます。
さらに、生涯学習人材バンクの利用促進を図るとともに、燕市美術展覧会の各部門に高校生を対象とした賞を創設することにより、幅広い世代の市民が芸術に触れる機会と発表の場を提供いたします。
併せて、燕市立図書館の空調設備等の改修工事や吉田北体育文化センターの体育館棟特定天井の耐震工事、両施設のトイレの洋式化工事などを実施し、利用者が安心して快適に利用できる環境を整備します。
基本方針2 支え合い・助け合い活動の活発化
活動人口増戦略の2つ目の柱は、「支え合い・助け合い活動の活発化」です。
施策1 支え合いの地域福祉
最初に述べましたとおり、子どもの貧困問題に対応するため、子どもたちが夢と希望を持ち健やかに成長できるよう、新たに推進体制を整備し、相談体制の充実や周知活動などの対策を講じてまいります。また、家庭児童相談員による生活困窮世帯等への家庭訪問に「子どもたちへの学習環境改善支援」を追加します。
2018年度からスタートする「第3次燕市地域福祉計画」に基づき、地域で安心して暮らすことができる地域共生社会の実現に向けて、地域の支え合い・助け合いによる体制づくりを進めてまいります。
施策2 市民協働のまちづくり
「市民協働のまちづくり」の推進につきましては、まちづくり協議会や市民団体の活動のさらなる活性化を図るため、引き続き「イキイキまちづくり支援事業」等による事業費助成や情報提供、課題解決に向けた支援を行います。
また、条例で規定されている見直し時期の到来に基づき、「燕市まちづくり基本条例」の見直しの要否等について検討を行います。

基本方針3 若者・女性の力を活かしたまちづくり
活動人口増戦略の3つ目の柱は、「若者・女性の力を活かしたまちづくり」です。
施策1 若者の活動の活発化
はじめに「若者の活動の活発化」についてでありますが、「つばめ若者会議」の29歳以下のメンバーによる「燕(エン)ジョイ活動部」のサポートを中心に、若者の主体的な活動や地域団体等と連携した取り組みの支援を行うなど、若い世代のまちづくりへの関心・意欲の向上を図ります。


また、中高生を対象として、情報発信することを通じて燕市について学び、郷土を深く知ってもらう「つばめいくプロジェクト」を継続します。

施策2 女性が活躍しやすい環境づくり
次に、「女性が活躍しやすい環境づくり」についてであります。
「第3次燕市男女共同参画推進プラン」に基づき、意識醸成を図るための啓発イベントを開催するほか、「女性が輝くつばめプロジェクト推進事業」では、新たに若手職員を対象とした異業種交流研修を開催するとともに、市内事業者と協働し女性活躍推進フォーラムやイクボス研修会等を開催します。

また、働く女性の代表として働きやすい職場環境の整備について検討するプロジェクトチーム「活働☆つばめこまち応援隊」の活動を支援してまいります。
戦略3 交流・応援(燕)人口増戦略
戦略の第3は、交流・応援(燕)人口増戦略であります。
燕市を訪れたい・応援したいと思う人を増やすため、
- 着地型観光の振興、
- 都市間交流の推進、
- 燕市のファンづくり
に取り組みます。
基本方針1 着地型観光の振興
交流・応援(燕)人口増戦略の1つ目の柱は、「観光の振興」です。
施策1 着地型観光の振興
産業史料館については、燕市の産業観光の拠点として機能強化を図るため、本館の展示リニューアル、体験工房館の新設、広場の改修などの工事を行い、平成31年(2019年)4月のオープンを目指します。
なお、産業史料館を含めたエリア全体の魅力向上を目指した「県央大橋西詰周辺地域整備事業」については、大曲堤防道路の整備や県央基幹病院整備による土地開発需要の中長期的な動向を見極める必要を踏まえ、事業を一旦停止し、その在り方を慎重に検討してまいります。当面の間は、取得した事業用地を簡易造成したのち、産業史料館の魅力アップ策を活かした試行的イベントの開催や、周辺公共施設利用者のための臨時駐車場に活用いたします。
また、燕市観光協会と連携し、分水おいらん道中や酒呑童子行列などの各種イベントを実施するほか、ボランティアガイドへの活動支援や、外国語を話せる観光ナビゲーターを活用することで、着地型観光のさらなる推進に取り組んでまいります。
弥彦村と連携し、首都圏からの誘客はもちろん、訪日意欲が高いとされている台湾人旅行客を増やすための観光プロモーションを実施するほか、燕三条駅から市内の工場や良寛史跡等を巡る観光タクシーを運行し、二次交通不足の課題解消に努めます。


さらに、「産業観光受入体制整備事業」では、増加する産業観光のニーズに対応するため、製造現場の一般公開に必要な費用の一部を補助するほか、三条市と連携して行う「燕三条工場の祭典」についても、より内容を充実して実施いたします。
基本方針2 都市間交流の推進
交流・応援(燕)人口増戦略の2つ目の柱は、「都市間交流の推進」です。
施策1 都市交流・広域連携の推進
災害時相互応援協定を締結している南魚沼市、南相馬市、南陽市との交流では、昨年度に引き続き、燕三条地場産業振興センターと連携したイベント出展を行うことで地場産品のPRを推進します。
また、東京ヤクルトスワローズとの縁で始まった松山市、浦添市、西都市との交流についても、今年度は燕市で開催される少年野球大会等を通して、より深い交流を目指すとともに、相互のイベントに出展することで地域活性化に結びつけていきます。
さらに、定住自立圏共生ビジョンに基づいた弥彦村との連携や、連携中枢都市圏の形成に係る協約に基づいた新潟市との連携を進め、生活の利便性向上や観光振興に取り組んでまいります。
基本方針3 燕市のファンづくり
交流・応援(燕)人口増戦略の3つ目の柱は、「燕市のファンづくり」です。
施策1 イメージアップ・ふるさと応援
「ふるさと燕応援事業」につきましては、お礼の品を通じて燕市の認知度の向上に大きく貢献しており、引き続き本市を全国にPRしていきます。さらに、本市の事業に賛同する人からも応援してもらえるよう、クラウドファンディング型の仕組みの導入や、高齢者見守り支援を寄附対象とするなど、新たな取り組みも展開します。
燕市を紹介する新たなガイドブックの活用や「燕市PR大使」の活動により全国に本市の魅力を発信するとともに、明治神宮野球場におけるPRイベント「燕市DAY」の開催や球団ファンとの交流事業の実施による東京ヤクルトスワローズとの連携事業など、特色あるシティプロモーションを推進します。


戦略4 人口増戦略を支える都市環境の整備
戦略の第4は、3つの人口増戦略を支える都市環境の整備であります。
- 安全・安心機能の向上、
- 快適な都市機能の向上
という2つの方針に基づき取り組んでまいります。
基本方針1 安全・安心機能の向上
都市環境整備の第1の柱は、「安全・安心機能の向上」です。
施策1 災害に強いまちづくり
はじめに、「災害に強いまちづくり」についてであります。
自主防災組織の育成・支援のため、地域に根ざした防災活動を支援する補助事業や防災リーダー養成講座を継続するとともに、新たに女性対象の講座を開催します。

総合防災訓練については、昨年と同様7月の第1日曜日に、市民の皆さんと市職員の防災力がさらに向上するよう、より実践に即した内容で実施します。

また、新たな洪水浸水想定に基づいたハザードマップを出水期前までに全世帯に配布し、市民の皆さんから地域の危険度について認識していただく中で、災害への備えの定着を図ります。

さらに、地域の基幹的避難所に、食料・飲料水などの災害用備蓄品を計画的に配備するとともに、高齢者やアレルギーに対応した食品の配備も進めます。
施策2 防犯・消費者保護対策の推進
次に、「防犯・消費者保護対策の推進」についてであります。
引き続き、地域で設置する防犯カメラの設置費用を補助するとともに、警察などの関係機関と連携して、安全で安心なまちづくりの実現を目指します。
増加する高齢者の消費者トラブルやIT関連など複雑多様化する消費生活相談に対応するため、相談窓口の一層の充実を図るとともに、消費者被害の未然防止のための周知活動に取り組みます。
施策3 交通安全の推進
次に、「交通安全の推進」についてであります。
高齢者が関与する交通事故の割合が高いことから、「高齢者運転免許自主返納への支援」を継続するとともに、燕警察署及び燕市交通安全協会と連携し、交通安全教室や街頭指導の充実、交通安全意識の啓発に努め、交通事故の抑止に取り組みます。
施策4 公共交通の整備
次に、「公共交通の整備」についてであります。
循環バス「スワロー号」や弥彦村と共同で運行する「やひこ号」、予約制乗合ワゴン車「おでかけきららん号」を運行するとともに、民間バス路線への運行費補助を引き続き実施し、効率的で利便性の高い公共交通環境を提供してまいります。


また、「燕市公共交通基本計画」の計画期間が終了することから、市民ニーズを反映しつつ、費用対効果の点でもバランスのとれた運行ネットワークを弥彦村とともに形成するため、「燕・弥彦地域公共交通網形成計画」を策定します。
施策5 快適な環境の確保
次に、「快適な環境の確保」についてであります。
「クリーンアップ選手権大会」や「つばめエコキッズ探検隊」など、環境啓発イベントの開催を通じて、地球温暖化や身近な環境問題について考える機会を提供します。

(つばめエコキッズ探検隊)」
また、「小型家電リサイクル推進事業」、「ペットボトルリサイクル推進事業」、「カンカンBOOK事業」などを引き続き実施するほか、昨年度にスタートした「福服BOOK事業」については、古着等の回収場所を市役所駐車場に変更し、毎日の回収を可能にするなど、さらなる資源循環型社会の構築を図ります。

(小型家電リサイクル推進事業)
基本方針2 快適な都市機能の向上
都市環境の整備の第2の柱は、「快適な都市機能の向上」です。
施策1 まちなか居住と空き家等対策の推進
はじめに、「まちなか居住と空き家等対策の推進」についてであります。
人口減少・高齢化社会に対応するため、「燕市立地適正化計画」に基づき、まちなか居住を推進することで、持続可能なまちづくりを進めてまいります。
年々拡大する空き家等の問題に対処するため、実態調査を継続するとともに、専門家の関係団体で構成する「空き家等対策連絡協議会」において、空き家総合相談会やセミナーを開催するなど、相談体制の充実を図ります。
また、市民の安全・安心を確保するため、周囲に悪影響を及ぼしている特定空き家の「旧南楽新館」と「旧新潟惣菜食品」の2件を除去し、その後の跡地利用につなげてまいります。
さらに、民間の力を活用したまちなか活性化の仕組みづくりを検討するため、新潟大学と連携し、学生と地域住民が連携した「まちあるき」による実態調査や、空き家・空き店舗・空き地の活用に関するワークショップなどを実施します。
施策2 親しみのある公園づくり
次に、「親しみのある公園づくり」についてであります。
吉田ふれあい広場においては園路等のバリアフリー化を引き続き実施し、燕市交通公園では経年劣化した連絡橋の更新を行います。
また、都市公園の維持修繕基準の法令化に伴い、遊具のより厳格な点検による事故防止の観点から、新たに国家資格者による専門的な検査を実施します。
施策3 人にやさしい道路環境の整備
次に、「人にやさしい道路環境の整備」についてであります。
通学路の安全を確保するため、新潟交通電鉄跡地や2018年度に供用開始予定の国道289号燕北バイパスに接続する道路の歩道整備などを実施するほか、新たに分水地区に整備する保育園の周辺道路の改良工事を行います。
さらに、国道116号吉田バイパスの整備については、引き続き地元の商工団体や土地改良区、自治会などの各種団体と連携し、早期の都市計画決定及び事業化を国・県に働きかけてまいります。

施策4 安全・安心・おいしい水道水の供給
次に、「安全・安心・おいしい水道水の供給」についてであります。
弥彦村との「水道事業の統合に関する基本協定」の締結を受けて、事業統合への具体的協議を進めるとともに、「燕市・弥彦村水道事業広域化基本計画」に基づき、平成37年度(2025年度)の供用開始を目指し、統合浄水場を建設するための基本設計などを実施してまいります。

また、平成35年度(2023年度)までに、石綿セメント管の完全廃止を目指して、計画的に更新を進めます。
施策5 適正な汚水処理の推進
次に、「適正な汚水処理の推進」についてであります。
効率的で持続可能な汚水処理施設の整備を進めるため、2016年度から進めている「燕市汚水処理施設整備構想」の策定の完了を目指すとともに、下水道施設の計画的・効率的な整備を進めるほか、引き続き終末処理場の改築更新や、本町排水区における幹線管渠の改修を行います。
また、接続率の向上を図るため、早期接続報奨金の交付を継続いたします。
戦略5 持続可能な行財政運営
最後に戦略の第5、持続可能な行財政運営についてであります。
限られた財源の中で第2次総合計画に掲げた施策を着実に進めていくためには、多様化する市民ニーズや地域課題を的確に把握し、不断の行財政改革を推進していくことが求められます。
新年度においては、タブレット型パソコンを活用するペーパーレス会議を推進するなど、資料の電子化による印刷コスト等の削減及び保管管理の効率化を図ります。
また、社会教育施設の使用料について、施設及び地区間の不均衡等を是正し、適正な価格に改定するための見直し作業を引き続き進めてまいります。

さらに、職員個々の能力や組織の力を高めるとともに、働き方を見直すことで、職員の長時間勤務の是正や市民サービスの向上につなげてまいります。
むすび
以上、2018年度の市政運営の基本方針並びに主要事業について申し述べてまいりました。
2016年度の施政方針でも触れましたが、2015年10月実施の国勢調査によれば、5年前と比較した人口増減率は、燕市は県内30市町村の中で良い方から5番目、20市では新潟市に次いで2番目に良い結果となりました。
また、最新の公表データである2015年の製造品出荷額等が4,413億円となり、リーマンショックで2009年に3,360億円にまで落ち込んだところから見事にV字回復し、リーマンショック前(2008年)の4,309億円を超えました。
さらに、燕市に寄せられる「ふるさと納税」については、昨年度まで3年連続新潟県内一位、今年度も既に9億3千万円を超えています。
今年の干支は、「戊戌(つちのえ・いぬ)」です。「絶頂期」と「枯れる」という二つの意味が重なる、明暗がはっきり分かれる分岐の年と言われています。
そうした意味において2018年度は、これまで積み重ねてきた人口減少対策や地方創生の取り組みの成果を枯らすことなく、さらに磨きをかけ、次なる未来へ確実に進んでいくための重要な年度であると私は考えています。
長善館に代表される「人づくり」、国上山や大河津分水路に代表される「自然」、日本有数の製造業が集積する「産業」、この三つが調和する燕市の魅力をさらに磨き上げ、より強力に情報発信しながら、子どもたちが未来への夢や郷土への誇りを持てる「日本一輝いているまち・燕市」の実現に向け、引き続き職員一丸となって誠心誠意取り組んでまいります。
市民の皆様並びに市議会議員の皆様におかれましては、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げ、2018年度の施政方針とさせていただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画財政部 企画財政課 企画チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8352








更新日:2021年03月01日